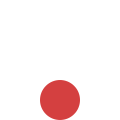育成協会の強み
40年を超える歴史と累積顧問数3,000社の実績
中小企業一筋で実績を積み重ねてきた私たちの強み
-
やらせていただきます主義
ご依頼があったから、必要だと言われたからという受け身の姿勢ではなく、常に企業様にとって「なにが必要か」や「背景」を考え、職場環境をよりよいものにしていくため、やらせていただくという意識を持って業務にあたっています。
-
膨大な過去の事例
育成協会は設立40年以上社労士事務所および事業主のための組合である「労働保険事務組合」として活動してきました。顧問数も累計で3,000社になります。この膨大な経験があるからこそ、多くの状況に細やかな対応ができます。企業様にとっての「困ること」「やってほしいこと」を3,000社分、私たちは体験しています。
-
会社に合ったサポート
複数名の社労士が在籍しており、手厚いサポートが行えることも育成協会の強みです。一つのご相談に対し、一人の社労士が全ての解決方法を見出すのではなく、チームで最良の提案に向けて取り組みます。経営者様の求めるサポート体制(メールで細かく対応してほしい、会って話したいなど)を構築しています。
経営者の悩みや耳寄りな情報の共有を積極的に行います。
経営者の悩み
会社経営において「困ること」「悩むこと」をご紹介します。会社の数だけ困難や悩みがあります。他の企業様の悩みが自社の悩みと似ていたときには、大きなヒントになります。
-
- ポイントは労働時間の管理!2024年問題の処方せん【トラック輸送業界編】
時間外労働上限規制の導入
長距離輸送など、長時間労働が常態化している運送業では、2024年3月末までの5年間にわたる働き方改革関連法の猶予期間が終了し、トラック運転手の時間外労働上限が年960時間(月平均80時間。休日労働を除く)に制限されます。これはトラック運転手も労基法を遵守し、通常の労働者として時間管理する必要があることを意味します。
この課題を放っておくと、法令違反による罰金(違反者一人当たり30万円)を課せられる、風評被害による採用への影響が出る等、企業経営にとってのリスクにつながります。
上限規制対応にITツールが効果的
上限規制の適用に向け、長時間労働の是正に限らず、特に中小の物流企業ではあらゆるシーンで変革が求められるでしょう。このようなときに重要なのは、ITツールを活用した業務の効率化ではないでしょうか。トラック輸送業に適したツールを見ていきましょう。
■勤怠管理システム
勤怠管理システムを導入することにより、労基法に基づく労働時間に加え、改正基準告示(後述)を遵守して休息時間、連続運転時間、2日平均・2週平均の運転時間なども管理できます。タイムカードや運転日報、運行記録のデータを表計算ソフトに転記し、集計を行うための労力と時間が不要となります。
拘束時間のアラート設定機能を活用すれば、残り時間数を把握することもできます。
■配車支援システム
トラック輸送では積載量や運転時間も守らなければなりません。「配車支援・計画システム」は、手作業で行っていた配車業務をシステムに入力することによって、自動で配車計画を策定します。その効果として、効率的な配送ルートの策定、車両台数の最適化、過積載の防止、配車作業の短時間化等が挙げられます。労働時間の平準化に加え、積載率・稼働率の向上が期待できます。
■乗務後の自動点呼機器
物流企業では、運行の安全確保のため、運転手に対し原則として人の対面による点呼が義務付けられていますが、令和5年1月より、乗務終了時の点呼を自動で行えるようなりました。導入の要件は、(1)国交省認定機器の使用、(2)運輸支局長等への事前届け出の2点です。点呼のために人を配していた場合は、人件費の削減にもつながります。機器導入に当たっては、全日本トラック協会の自動点呼機器導入促進助成事業を通じ、助成金を申請することもできます。
なお、ITツール導入に際しては、中小企業・小規模事業者の業務効率化やDX等を支援するIT導入補助金を利用すれば、最大で経費の半額に対して補助金を受けることができます。
改正基準告示
2024年4月より厚生労働大臣の改善基準告示も改正され、年間及び1か月の拘束時間、1日の休憩時間が見直されます。

ITツールの積極的な活用は、デジタルネイティブと言われる若い世代の求人にも効果的です。事業の継続、拡大に向けて、2024年問題に取り組むことが急務です。育成協会へお気軽にご相談ください。
-
- 待ったなし!2024年問題に向けた取り組み【建設業編】
働き方改革による罰則を伴う時間外労働の上限規制は、対応が難しいとされていた建設業、自動車運転の業務、医師も2024年4月から猶予期間が終了し、適用となります。
今回は建設業の取り組みについて、お伝えします。
建設業は、元々今後担い手である団塊世代の大量離職が見込まれており、全産業平均と比較して年間300時間以上の長時間労働を余儀なくされている事実(2016年度)や、他産業では主流となっている週休2日取得も厳しい状況があります。一方、働き方改革が進んでいる他業種への人材の流出が進み、採用状況は深刻化しています。結果として事業継続が困難だと感じている建設業経営者の方は少なからずおられることと思います。
特に建設業は3Kとも言われる労働環境から若い世代に敬遠されがちで、会社の将来を担う若手の人材の確保が難しくなってきていると言われてきています。しかしながら、彼らの多くはワークライフバランスや、ゆとりある就業環境を望んでいる一方、近年はスキルアップを重視するタイプも増えてきています。このタイプは仕事を通じて能力を伸ばし、適正な評価を受け、しっかり収入を得ることを望んでいます。彼らにとって、仕事をしながら様々な資格に挑戦でき、かつ仕事の成果が形となって現れる建設業は、魅力的な業種とも言えます。受け入れ企業としては勤怠管理や書類作成をサポートするITツールを導入して極力間接作業を減らしたり、資格取得奨励制度を設けたりすることで、彼らがスキルアップを実感できる働き甲斐のある職場環境を整えることが採用力を高めることに繋がると考えられます。
人材の定着を図り、業績を拡大していくために、この働き方改革をチャンスと捉え、取り組んでみられてはいかがでしょうか。育成協会の社労士チームへお気軽にご相談ください。